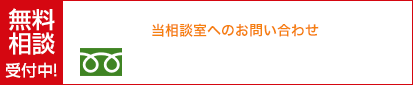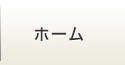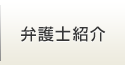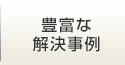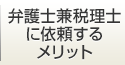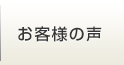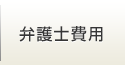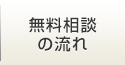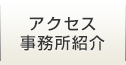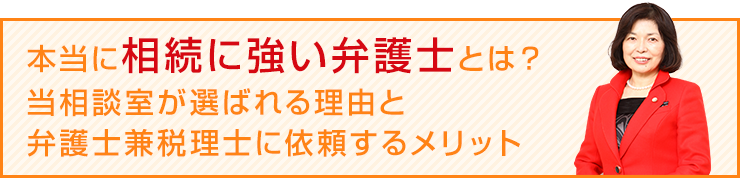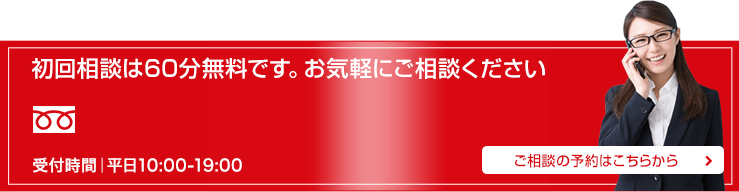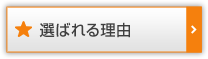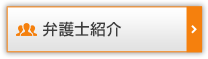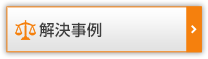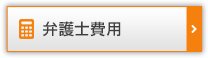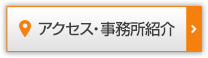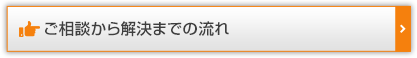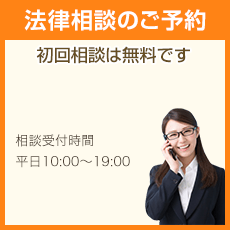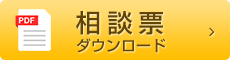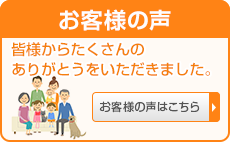法定相続と指定相続
こちらのページでは法定相続と指定相続についてご説明します。
法定相続について
民法(相続法)は、遺言が存在しない場合の各法定相続人の相続分を規定しています。
指定相続について
被相続人は、遺言で、共同相続人の全部または一部の相続分について、上記の法定相続分とは異なる割合を決めることができます。これを指定相続と言います。
但し、遺留分の規定に反する内容の遺言を定めると、遺産を取得できない相続人(または遺留分を下回る財産しか取得できない相続人)から遺留分侵害額請求をされる可能性が高くなります。
弁護士による無料相談を実施しております
弁護士による相続の相談実施中!
 当相談室では、初回相談は60分無料となっております。
当相談室では、初回相談は60分無料となっております。
「遺産分割でトラブルになってしまった」
「不安なので相続手続きをおまかせしたい」
「子どもを困らせないために生前対策をしたい」
などのニーズに、相続に強い弁護士がお応えいたします。
無料相談はお電話(0120-202-111)または問い合わせフォームより申し込みいただけます。
お気軽にご相談ください。
相談の流れについてはこちら>>>
メールでの相談予約は24時間受け付けております。
当事務所の相続問題解決の特徴
1、初回無料相談であらゆる相続のご相談に対応
2、相続の委任事項は安心の定額報酬制度を導入
3、遺産分割協議で係争になっても安心解決で費用割引
4、法律専門知識と不動産の専門知識で節税をご提案
5、他士業が敬遠する難しい相続手続や国際相続にも対応
お早目に弁護士に相談いただくことで、相続や遺産分割問題の早期の解決につながります。
無料相談はお電話(0120-202-111)または問い合わせフォームより申し込みいただけます。
お気軽にお申込みください。
この記事の監修者

弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)
小林 幸与(こばやし さちよ)
〇経歴
明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。
日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。
豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。